国際相続の手続き完全ガイド!専門弁護士が詳しく説明

近年、国際結婚や海外移住が増えるにつれて、国際相続の相談が増加しています。「海外に住む親が亡くなったけれど、どの国で手続きをすればよいかわからない」「海外に銀行口座や不動産がある場合、どうやって手続きを進めればいいのか不安」「外国にいる相続人と連絡が取りにくく、遺産分割の話し合いが進まない」といった悩みを抱えている方が増えているようです。
国際相続では、国によって法律や税制度が異なるため国内相続に比べてさらに複雑です。
この記事では、国際相続の基本から手続きの流れ、そして専門弁護士に相談するメリットまでを詳しく解説します。国際相続で悩んでいる方がスムーズに手続きを進められるように、具体的な方法をわかりやすくご説明します。
1. 国際相続とは?

国際相続とは、相続財産や相続人が日本国内だけでなく、海外にもまたがっている場合に発生する相続を指します。
国内相続との違いは、適用される法律や税制度が国によって異なることです。日本国内の相続であれば、日本の民法に従って遺産の分割や相続税の計算が行われます。しかし、国際相続では、相続財産が存在する国や被相続人が住んでいた国の法律が適用されることもありえます。
たとえば、日本に住んでいる方がアメリカに不動産を所有していた場合、不動産に関する法律関係はアメリカの法律が適用されます。一方で、現金や動産などの財産については日本の法律が適用されることもあります。
このように、財産の種類や所在地によって適用される法律が異なり、専門知識がないと対応の難しい案件が多くなりがちです。
2. 国際相続に関わる法律と適用法
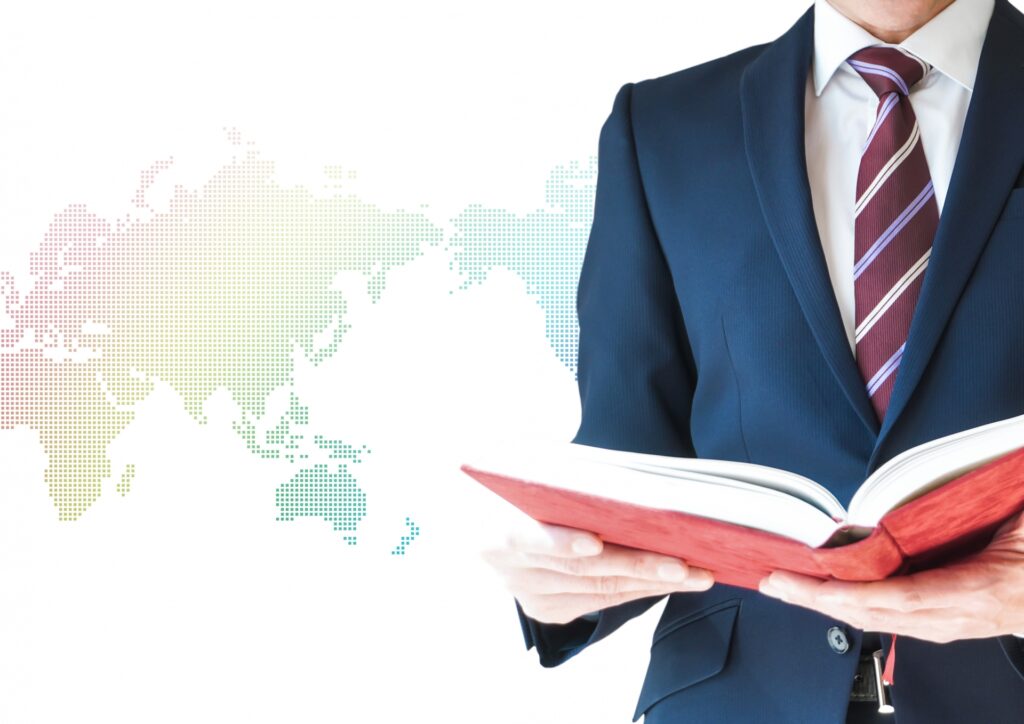
国際相続では、どの国の法律が適用されるのかを正確に判断する必要があります。
各国で異なる相続法
国ごとに法律が異なるため、相続財産の内容や所在地によって異なる法律が適用されます。
ハーグ条約や各国の民法、遺産税に関する法規制
国際相続には「ハーグ相続条約」などの国際条約が適用される場合があります。相続に関する国際的なルールが統一されている場合があるのです。
しかし、相続税や遺産税に関しては、各国で税制度が異なるため、相続人が税務上の問題に直面することがあります。
どの国の法律が適用されるかを判断する基準
どの国の法律が適用されるかを判断する際には、以下の基準が考慮されます。
- 被相続人の国籍
- 被相続人の居住地
- 相続財産の所在地
例えば、日本に住んでいた被相続人がアメリカに銀行口座を持っていた場合、銀行口座に関する相続手続きはアメリカの法律が適用される可能性があります。
3. 国際相続の基本的な手続きの流れ

国際相続の手続きは、国内相続に比べて複雑で、時間や労力もかかります。特に、相続財産や相続人が複数の国にまたがる場合、それぞれの国の法律や税制度に従って手続きを進めなければなりません。
ここでは、国際相続における基本的な手続きの流れを詳しく説明します。
死亡診断書の取得と翻訳
相続手続きの第一歩は、被相続人が亡くなったことを証明する「死亡診断書」の取得です。
被相続人が日本国内で亡くなった場合は、医師が発行する死亡診断書をもとに市区町村役場で「死亡届」を提出します。死亡届が受理されると「死亡受理証明書」を取得できます。
しかし、被相続人が海外で亡くなった場合は、現地の医療機関や役所で発行された死亡診断書を取得しなければなりません。死亡診断書が現地語で書かれている場合は、日本語への翻訳が必要です。
相続財産の調査
相続財産、すなわち被相続人が所有していた財産の範囲や内容を正確に把握する必要があります。相続財産には、以下のようなものが含まれます。
- 現金や預金(日本国内・海外の銀行口座)
- 不動産(自宅、土地、マンションなど)
- 株式や投資信託
- 自動車、貴金属、美術品などの動産
- 負債(ローン、クレジットカードの未払い分 など)
財産の所在地によって、どの国の法律が適用されるかが異なるため、まずは財産の詳細を正確に把握することが重要です。
また、海外にある不動産の登記や銀行口座の名義変更には、現地の法律に基づいた書類が必要になる場合もあります。こうした書類を準備する際には、現地の弁護士や金融機関のアドバイスを受けるとスムーズに進められます。
遺言書の確認
被相続人が遺言書を残している場合、その内容を確認する必要があります。
遺言の成立当時の遺言者の国籍国の法律に従って有効性が判断されます。
また、遺言書が無効と判断された場合は、法定相続分に従った相続手続きが必要になります。
相続人の確定
相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書などが必要になります。
日本では配偶者と子どもが優先的に相続権を持ちますが、国によっては兄弟姉妹や親も相続人になることがあります。
遺産分割協議
相続財産の内容と相続人が確定したら、財産分割協議を行います。
相続人が全員日本国内にいる場合と比較し、相続人が海外にいる場合はオンラインでの話し合いや弁護士を通じた協議など、話合いの場をもつだけで大変な場合があります。
税務申告と納税
国際相続では、相続税や贈与税の申告と納税が必要になりますが、申告期限や必要な書類は国によって異なります。
相続税が課税される国が複数ある場合、租税条約に基づいた控除や減免措置を受けることで二重課税を回避できる場合があります。
このように、国際相続では国内相続にはない独自の手続きやルールが数多く存在します。全て初心者には難しく、専門弁護士や現地の法律家の協力が欠かせません。
4. 国際相続を専門弁護士に依頼するメリット

国際相続は国内相続に比べて法律や税制が複雑です。特に、相続財産や相続人が複数の国にまたがっている場合や、相続税の計算が異なる場合には、弁護士にサポートを依頼しましょう。
各国の法律に詳しい弁護士が適切なアドバイスを行う
国際相続では、相続財産が存在する国や被相続人が住んでいた国によって適用される法律が異なります。
日本の弁護士が現地の法律に精通しているケースは限られるため、国際相続を専門とする弁護士は、現地の法律に詳しい弁護士や法律事務所と提携して適切なアドバイスを提供します。
煩雑な手続きをスムーズに進められる
専門弁護士に依頼すれば、必要書類の取得や翻訳、公証手続きを代行してもらえるため、相続人の負担が大幅に軽減されます。また、現地の弁護士や金融機関とのやり取りも専門弁護士が代行してくれます。
相続税や贈与税の二重課税を防ぐサポートを受けられる
国際相続では、相続財産が存在する国ごとに相続税や贈与税が課税されるため、二重課税のリスクがあります。専門弁護士は、租税条約の内容や適用範囲に詳しく、適切な申告方法や税額控除のアドバイスを提供します。これにより、余分な税金を支払わずに済む可能性が高くなります。
相続人間のトラブルを回避・解決できる
国際相続では、相続人が複数の国に住んでいる場合や、適用される法律が異なるためにトラブルが発生することがあります。
専門弁護士は、こうしたトラブルを中立的な立場からサポートし、公正な立場で遺産分割協議を進めます。話し合いで解決しない場合には、裁判や調停に発展することもあり、弁護士を通して手続きを進めるとなにかと安心です。
現地の専門家とのネットワークを活かした対応が可能
国際相続に対応できる弁護士は、現地の法律事務所や金融機関と提携していることが多いため、必要に応じて現地の専門家と連携したサポートが可能です。
例えば、アメリカに不動産を所有しているケースでは、現地の不動産登記手続きや税務申告が必要になる場合があります。このような場合でも、現地の法律に詳しい弁護士や税理士と連携し、正確かつ迅速な手続きが可能になります。
5. 国際相続の手続きをスムーズに進めるために

国際相続の手続きをスムーズに進めるためには、専門弁護士への相談を強くお勧めします。
国によって異なる法律や税制度に対応するためには、現地の法律に詳しい専門家の協力が欠かせません。
国際相続に強い弁護士に相談すれば、現地の法律や税務に関する最新の情報をもとに適切なアドバイスを受けられます。
「弁護士に相談しておけば安心」「すべて任せられるから心強い」という気持ちを持てることが、専門弁護士に依頼する最大のメリットです。トラブルなくスムーズに国際相続を進めるために、早めの相談をおすすめします。
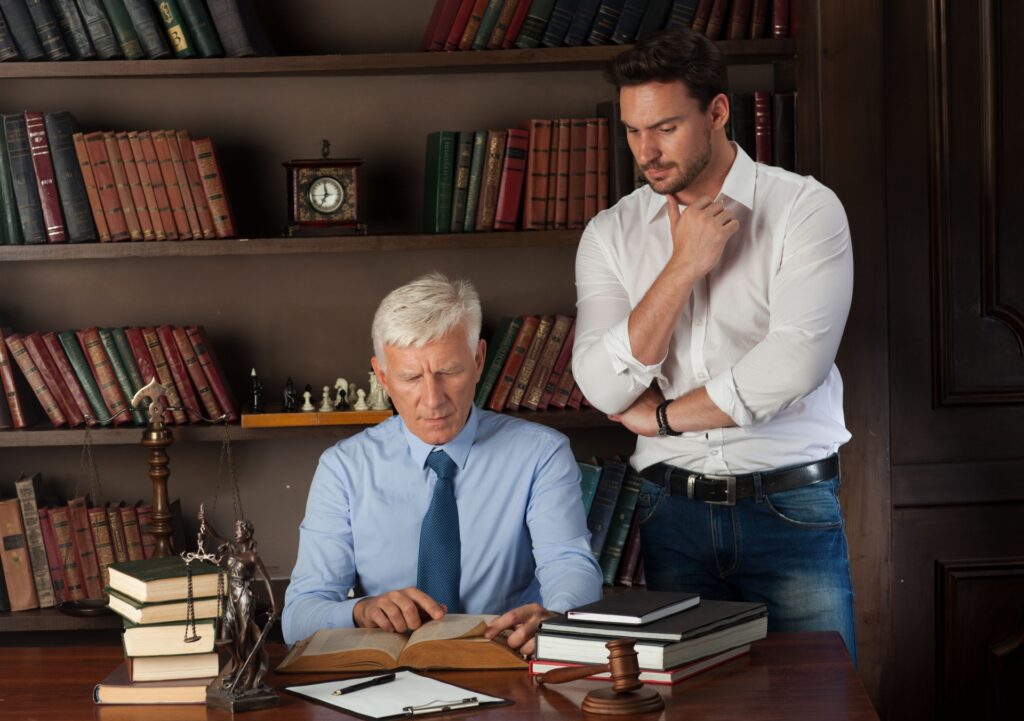


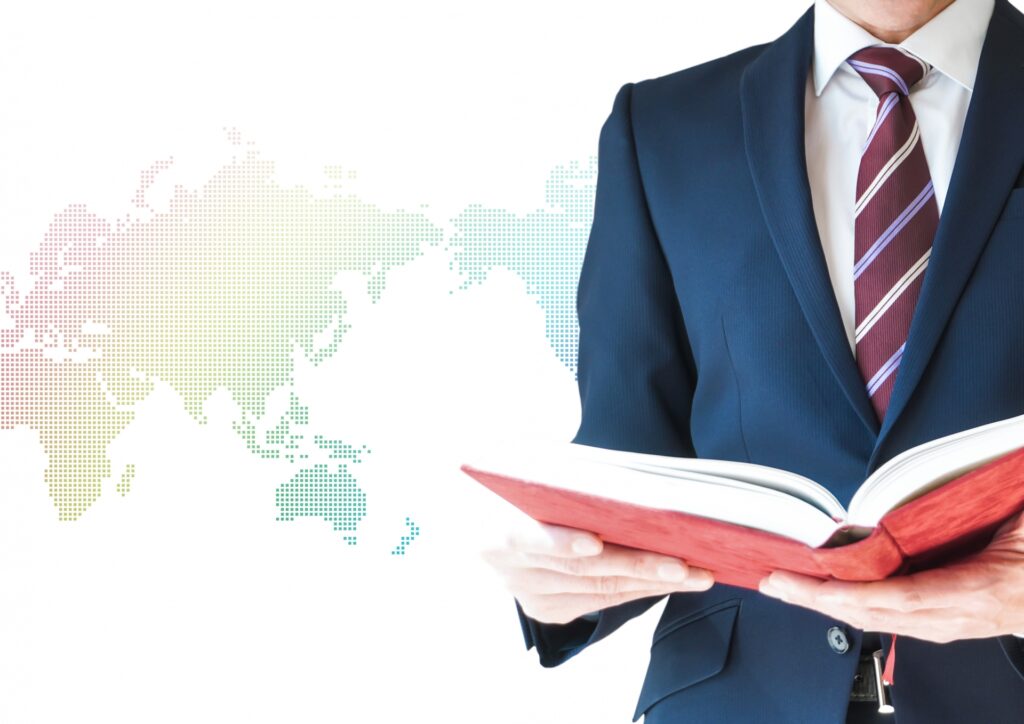






コメント
この記事へのトラックバックはありません。







この記事へのコメントはありません。